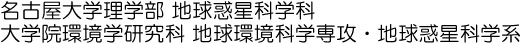学生の声
在校生の声
| 江藤 周平 さん (地球惑星ダイナミクス講座 前期課程1年) | |
| 私は他大学から名古屋大学大学院に入学し、学部から引き続き大学院でも地殻変動観測に関する研究をしています。そこで私は他大学から大学院進学を考える人に向けてアドバイスをしたいと思います。 私が大学院受験を考えたときにしたことは情報収集でした。名古屋大学以外にも興味を持った大学院のオープンキャンパスに行き、院生や教員に話を聞いて試験対策(お勧めの参考書など)や院生生活(授業やセミナー)などについて調べましたし、それ以外にも興味ある先生のところへ個別に訪問しじっくりとお話したりもしました。試験勉強は過去問(専門と英語,webでダウンロード可)を解き、教えていただいた参考書を読み進めました。 他大学への進学は不安なことがたくさんあります。内部生に比べて得られる情報も少ないですし、慣れない土地にいくわけですから。しかし新しい環境で得られる刺激や知識は大変良いものだと思います。ぜひ自分の足を動かしてみてください。 |
|
| 舟洞 久人 さん (地球環境システム学講座 前期課程1年) | |
 |
私は学部では化学を専攻していました。大学院への進学を考えるにあたって環境学研究科を知り、地球環境科学専攻では様々な分野をベースとした学生が集まって活発な研究が行われていることを知りました。事前に興味を持った研究室の先生と連絡を取り実際に研究室を訪問したときには、あまり環境について知識の乏しい私に対しても丁寧かつ熱心に話して下さいました。そこで学部時代の知識を生かしながら環境学に携わる道があること知り、現在の研究室へ進学しようと決めました。 受験に関して私は後期受験であり、受験に際しては研究室の先輩に英語をしっかり勉強するようアドバイスを頂きました。英語で書かれた教科書中の環境に関するコラム等を300ページ程読むことで英語の勉強とともに環境問題に対する知識を広げるよう努力しました。試験には英語の他にプレゼンもあるので発表前の準備も忘れないようにしましょう。 現在私は有機溶液栽培についての研究を行っています。まだまだ分からないことも多いですが自分で必要な情報を集めたり、先生や先輩方と意見交換をしたりしながら日々頑張って研究を続けています。これから受験を考えている皆さんも、この大学院で自分のやりたいことがあれば積極的にアプローチして下さい。 |
| 山田 真也 さん (地質・地球生物学講座テクトニクスグループ 前期課程1年) | |
| 私は広島大学から学部4年を経た後、地質・地球生物学講座に入学しました。私が名古屋大学に進学しようと思ったきっかけは、6月にあった名古屋大学の大学院入試説明会でした。卒業研究を行っていた中で、他大学の研究の様子などに興味を持ち、また友人から、他大学に訪問することはいい刺激になると言われ、名古屋大学の説明会を見に行くことにしました。これを受けて、新しい環境で研究するのもいいかなって思ったことがここを選んだきっかけの一つです。 試験では私はII期入試を受験しました。試験内容は英語と卒業研究の発表でした。英語の試験対策としては、和訳対策としては1日1つ英文を読み、英訳対策は英語のできる友人に添削してもらい、英訳のコツを教えてもらいながら勉強しました。卒業研究と並行して試験勉強するのは大変でしたが、毎日決めた時間内に勉強していたので、自信を持って試験に臨めました。 大学院に進学してからは、学部時代で行った後背地解析の続きを行おうと思っています。主に砂岩中に含まれる砕屑性ジルコン・モナザイトの年代測定や、砕屑性ザクロ石の化学組成分析を用いた後背地解析です。私はまだまだ勉強不足な点が多々ありますが、この大学院生活の中で少しでもその穴を埋め、充実した研究生活を送れるようにしっかり努力していきたいと思います。 |
|
| 小澤 萌 さん (地球化学講座 前期課程2年) |
|
| 2009年4月に地球惑星科学科の研究室に進学し早いもので1年が経ちました。 私は学部時代、北里大学の理学部化学科に在籍していました。学科が変わったことによって、入学当初は大小様々なカルチャーショックに見舞われたことを思い出します。一つは、実験器具を作るために装置開発室で実習を行ったことです。太い鉄棒を高速で回し、金属製のドリルをあてながら削る旋盤という機械を扱わせてもらいました。キュルキュルと削りかすが出てくる様子はとても面白く、これは化学科にいたら出来なかったことだと思います。さらに飲み会で4年生が「We are アンチゴラーイト!!(←鉱物名)」とはしゃいでいるのを見た時、あぁ違う学科に来たんだなとしみじみ感じたものです。 さて、私は今「隕石中のカルボン酸に衝撃を与えると、どのような変化を起こすのか??」というテーマで研究を行っています。 ここ半年以上、分析のためにごく微量のカルボン酸試薬を効率よくエステル化しようと色んな条件を検討してきました。収率がなかなか上がらなかったり、予期せぬ副産物が生じていたり、苦労したところはありますが最近ようやくまとまりつつあります。 研究を行う中で化学科で学んだことには随分助けられました。違う分野に乗り込むと今まで自分が持っていた感覚が有用に感じられたり、あるいは邪魔になることもありますが、学科で培った化学という視点は研究に役立っていると実感します。地球惑星科学は総合科目なので、違う学科出身の方でも自分が専攻してきた分野との接点を見いだせると思います。ある視点を持って異なる世界を覗き込み、その違いの中に驚きを感じるという面白さは他学科出身でなければ体感できないものでもあります。今の専攻が地惑でなくても思い切って飛び込んでみてください!! |
|
| 森 宏 さん (地質・地球生物学講座岩石学グループ 後期課程1年) | |
| 2年前に,山口大学から博士前期課程として地質・地球生物学講座に入学しました.前の大学では「付加体」,この大学では「変成岩」と少し研究対象は変わりましたが,野外調査を基本とするスタイルでフィールドを歩き続けています.もともと大学院に進学するのであれば,せっかくの機会なので,新しい環境で研究したいと思っていました.ただ,その思いは漠然としたものでした.受験のきっかけとなったのは,大学院説明会への参加です.ただ単純に実家から近く,ちょっと話を聞いてみようという軽い気持ちで参加しました.説明会の会場には様々な分野・講座の紹介ポスターが並べられ,ものすごい熱気でした.特別に「こんなことがしたい!!」というような考えはなく参加したので,とりあえず,自分の卒業研究テーマと関連の強い,現在所属する講座の説明を聞きました.説明していた先生から「なぜ違う大学院に進学したいのか?何がしたいのか?」と聞かれ,正直に「新しい環境に挑戦したい.とにかく野外調査のできる研究がしたい」と答えました.その思いを理解して貰えたのとともに,次のステップとして何が必要か,この大学に来たらどんなことが出来るのか等,親切なアドバイスも頂け,直感的に「ここで研究したい!!」と思い,受験を決めました. 環境を変えることは,不安も多く,すごく勇気がいることだと思います.実際,私も入学当初は「なぜここに来てしまったのだろう?」と悩むことも多々有りました.ですが,ふと自分が成長したことに気付いた時に挑戦してよかったと感じます.また多かれ少なかれ,異なる環境を経験していることは,自分自身の強みになっていると思います.もちろん,同じ大学で進学するにしても,環境を変えるにしても,どちらにもメリットはあると思います.ただ,少しでも環境を変えてみたいという気持ちがあるのなら,挑戦して損はないと思います.そして,環境学研究科・地球環境科学専攻は,様々な分野の人達が集まるとともに,設備も整っています.より専門性を高めたいと考えている人に,新しい分野に興味がある人に,また私のように異なる環境に身を置いてみたいと考えている人にも,進学先としてお勧めできる最適な場であると思います. |
|
| 川邑 圭太 さん (地質・地球生物学講座生物圏進化学グループ 後期課程1年) | |
 |
現在,私は植物プランクトンの1グループである珪藻の化石を用いて,過去5000万年間の赤道太平洋の海洋環境変動や生態系の変遷を明らかにしようと研究を行っています. 私は学部から名古屋大学に所属しており,卒業研究から現在の研究室で研究を続けてきました.研究室に配属されて卒業研究を始めた当初は,進学をするのかどうかも決めていない状態でしたが,一つ一つ地道に研究を重ねて今まで知られていない事実を明らかにしていく事の面白さに魅せられ,現在は博士後期課程へ進学して日々研究を重ねています. 本専攻には私たち学生自身が興味を持っている事を自分のペースで自由に研究させてくれる環境が整っていると思います.出来るだけ学生が考えている事を実現できる様に良く取りはからって下さり,教員の方々は学生が質問をすれば真剣に応じてくれます.また,学生同士でも各々の研究や新しい論文の内容に関して議論をしたり,次の実験や調査に関して互いに話してアイディアを出し合ったりする事もあります. 是非一度,名古屋大学の自由な空気の中で思う存分研究をしてみませんか?きっと,あなたの考える将来へと近づけると思います. |
| 村上 拓馬 さん (地球環境システム学講座 後期課程3年) | |
 |
私は,学部時代を東邦大学の化学科で過ごし,卒業研究に「フブスグル湖湖底堆積物中の無機成分を用いた古環境変動解析」と,化学科では異質なテーマを選択したことが,バイカル湖との出合いでした。 2003年には,金沢大学と共同で行われた21世紀COEサマースクールに参加し,念願のバイカル湖に行くことができました。ロシアでの6日間,中でも,バイカル湖の上で過ごした3日間は,忘れられません(最終日の嵐は特に…)。ショートコアや水のサンプリング,揺れる船内でのコアの切り分け作業を行 いました。早朝までかかったサンプリングのおかげ(?)で見ることができた朝日には,感動を覚えました。この巡検で得た経験や感動は,研究を続ける上で, 支えとなるでしょう。しかし,研究する中で,バイカル湖・フブスグル湖という巨大な自然の実験室から古環境を解析するには,まだまだ勉強不足を痛感させられます。 バイカル湖から昇り,バイカル湖に沈む太陽,そこから感じられる小さい自分。それは,過去と未来という長い時間の中の一端である現在の私を反映している ようでした。そんな私にできることは,まだまだ力不足ですが一歩一歩,着実に進み,バイカル湖を通じて,過去を知り,未来へと繋げる努力をすることだけです。 |
卒業生の声
| 利根川貴志さん (前期課程2005年修了,後期課程2007年修了) ハリケーン「リタ」から始まった留学 |
|
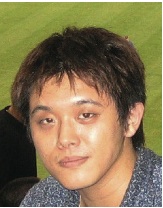 |
2005 年の9
月から地震学の研究のためにアメリカに留学をした。アメリカに行った当初は,住むところもなかなか決まらずかなり焦ってい
た。不安や寂しさもあったかもしれない。それが,あることがきっかけでまったくそういう気持ちがなくなった。それは9
月末にテキサスに上陸したハリケーン「リタ」。上陸の4
日前までは,大学の連中は「あれはたぶん進行方向を変えるよ」などと笑顔で話していたが,次の日,台風情報でリタがテキサスに上陸する可能性が高いと予報され,みんな大慌てで他の州に逃げる準備をしだした。そして,上陸前日には大学から大半の人が消えていた。さて,僕はどうするか。こっちに来て1ヶ月で,
逃げるところも情報もない。不安の絶頂期だったと思う。そのとき,大学からのメールで「大学にシェルターがあって,大学関係者はそこに入ることができます。また,食事も準備しています」という内容のものを見つけた。もちろん行く当てがなかったので,リタが上陸した夜は大学に避難してきた人たちとそこで一
緒に過ごした。 その経験以降,「なんとかなるものだな」という自信みたいなものが出てきて,生活に関してはあまり不安を感じなくなった。そういった意味では,9 月にヒューストンに来てよかったのかもしれない。ただ,もう二度とハリケーンは経験したくない。 |
| 常磐哲也さん (前期課程2004年修了,後期課程2007年満了) 私にとっての名古屋大学 |
|
 |
「何を話しているのだろう」というのが私の名古屋大学に対する初印象で
した。私は,修士課程まで和歌山大学教育学部に所属しており,名古屋大学を初めて訪れたのは,修士2
年の初めでした。それまで教育学部に所属していたこともあり,地球科学に関する専門授業をほとんど受けていなかった私にとって,名古屋大学の学生が話す研究内容は理解不能でした。このことに強い焦りを覚えた私は,とにかく前に進もうと思い,すぐに名古屋大学の受託研究生を希望し,地球惑星科学教室に籍を置かせていただきました。それからの私は,見るもの接するものすべてが真新しく,分からないことは調べ,それでも分からないことは羞恥心を捨て,周りに質問責めにしました。その頃の私は,「なんでそうなるの」というのが口癖でした。そして,ふと気づくと,もう博士後期課程が終わろうとしています。今でも相変わらずみんなの研究レベルの高さに圧倒される日々を送っていますが,周りの先生方や学友に支えられ研究を続けています。「初心忘るべからず」という言葉がありますが,私の初心とは,名古屋大学に始めてきた時に受けたショックと,そこから生まれた「とにかく前に進もう」という考えです。私は今年の4
月から研究職に就きます。そこでは,今まで以上にショッキングな経験をすると思いますが,名古屋大学の皆様から教えていただいた初心を忘れることなく常に
胸に抱き,日々精進していきたいと思います。(2006年,後期課程満了時の文章です。) |
| 戸上薫さん (地球科学専攻前期課程1997年修了) 意外に役立つ地球科学 | |
 |
平成9年に地球科学科を修了して既に10
年を経過した。在学当時は研究活動と実社会との接点が見いだせずに悩むこともあったが,いざ就職してみると,予想に反して地球科学科で学んだことは十年を通じて強力な武器となり続けた。地質コンサルタント会社勤務というわけではなく,窯業系建材メーカーを経て,現在は木造建築の設計・管理に従事しているにもかかわらず,である。 メーカーに入社してすぐ,修士論文で使った多変量解析を,陶器原料受け入れ時の合否判定に利用することができた。データは蓄積されているものの,統計的解析手法が導入されていない部署であったので,上司のウケはよかった。建築業界に転向してからも,地質に関する基礎知識は,建物地盤の解析に大いに役に立っている。講座を挙げて取り組む実習を通して,愛知県の地質の分布について講座全員が詳しくなったおかげだ。 地味だなァと思っていた3年生の頃の実習が,ジワリと効いてくることもある。実習では崖をハンマーで叩き岩石を採取したり,これを薄片とし顕微鏡で観察したりするなどして,体験的に岩石・鉱物に触れることができた。これが今,建材として使う御影石,大理石,大谷石,珪藻土などの素性を顧客に説明する時に 説得力の違いになって現れている。(これは独断かも。)ともかく,石の話をした後は,打合せがスムーズに運ぶことが多いのは確かである。「地球科学は,役に立つ。」今なら,はっきりこう言える。 |
| 榊原智康さん (地球科学専攻前期課程1998年修了) 架け橋 | |
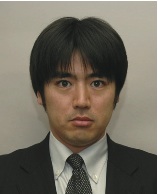 |
新聞社に就職して既に10
年を経過した。2つの支局を経て,現在は東京で科学記事の執筆をしている。 大学では地球惑星科学を専攻。地球化学講座で,自然界,特に河川での希土類元素の存在度パターンの変化などを研究した。研究内容は,今の仕事に一部役立ってはいるが,学会やコロキウムを通じて,プレゼンテーションの重要性を学んだことの方が,今の仕事に大いに役立っている。発表も記事も,分かりやすく人に伝える点では同じだ。 就職直後は社会部に所属していたため,取材でいろんな人と出会うが,理学部出身だと言うと,意外な顔をされることがよくある。新聞記者は文系出身者がなるものだと思っている人が多いようで, 「どうして,また記者に」との質問になる。 入社試験でも同じ質問を受けた。「科学と社会をつなぐ架け橋になりたい」。8年前,面接で緊張しながら,こう答えたことを覚えている。今もその気持ちは 変わっていない。 基礎研究や科学技術の現場と一般市民の乖離,子どもたちの理科離れが唱えられて久しい。記者としてキャリアを重ねていく中で専門分野を持ち,新聞というメディアを通して科学や技術への関心をかき立てるような仕事を,今後していければと考えている。 |