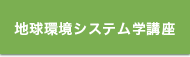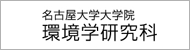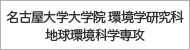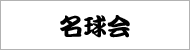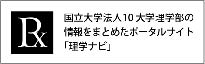新着情報
「地球環境科学と私」第五十八回
2025.10.10
「地球環境科学と私」第五十八回は 地質・地球生物学講座 松山 和樹さんによる かんらん岩を観る、マントルを覗く です.
かんらん岩を観る、マントルを覗く 地質・地球生物学講座 松山 和樹
学部4年次の研究室配属で岩石鉱物学研究室を選択した私は、卒業研究のテーマとして「かんらん岩」を与えられた。このテーマを承諾した最大の理由は「研究調査で北海道に行ける」という指導教官が用意した“ニンジン”であったが、博士後期課程に進学した現在でも、このテーマに取り組み続けている。本稿では、そんな蒙昧な学生が歩んできた4年半の研究を振り返る。
地表に露出しているかんらん岩の多くは、かつては上部マントルの一部であった物質であり、マントル内部での流動によって形成された「変形微細組織」を保存している。肉眼では粗粒で一様な塊状の物質に見えるかんらん岩であっても、詳細に観察すれば、しばしば鉱物の配列や形態に規則性が見いだされる。私が取り組む研究では、かんらん岩の分析によって、現代の科学技術ではアクセスできない上部マントルを”スナップショット“を撮るように覗くことで、マントルの実態の解明を目指している。かんらん岩研究はその性質上、覗く場所(かんらん岩を入手する場所)と、覗く手段(研究方法)の組み合わせによって無数の流派が存在するが、私は「北海道の山岳地域」で「変形微細組織の解析」を生業としている。本学の岩石鉱物学研究室の中だけで見ても、「マリアナ海溝」で「化学組成の分析」に取り組む学生もいるので、流派の違いは個人の性格の違いがよく反映されるのではないかと思う。私の場合、広いフィールドでの地質調査と、丹念な分析を要する変形微細組織の解析の組み合わせが、特に性に合っていた。
私の流派である“変形組織学”は、1960年代、構造研究の黎明期を支えた偏光顕微鏡を用いた組織観察に端を発する。この頃はまだ「かんらん岩の観方」が確立されておらず、組織観察は分類学的な側面が強かった。どのような場所で、どのような組織が存在するのかが整理され、その組織が形成されるシナリオが立てられた。研究方法自体は定性的であったものの、実験・野外調査・組織観察の知見が融合され、上部マントルの運動像が素描されたのがこの時代である。
その後2000年代に入ると,走査型電子顕微鏡(Scanning Electron Microscope,SEM)を用いた分析が登場し、定量分析が行えるようになった。中でも、ある程度広い領域で、鉱物の情報(鉱物の種類やその結晶構造、方位)の2次元分布を定量的に取得できる電子線後方散乱回折(Electron Backscattered Diffraction,EBSD)法は非常に強力で、分類学的な組織観察からの脱却を促し、“変形組織学”という流派を確立させた。EBSDの世界的な普及は、瞬く間に分析精度の向上と測定データの累積を加速し、上部マントルへの理解を飛躍的に進展させた。

図1. 岩石鉱物学研究室所有のSEM-EBSDシステム(岩石鉱物学研究室HPより)。
私の指導教官である道林克禎教授は、変形組織学の世界に魅せられてEBSDを日本の地質学コミュニティに持ち込んだ第一人者であった。そのような背景から、私の卒業研究は北海道日高山脈南端の幌満かんらん岩体で採取した13試料のEBSD分析がテーマとなった。EBSDを使って「ひとまずマントルを覗いた」この卒業研究は、学会発表でも多くの方に興味を持っていただいただけでなく、査読付き論文として国際誌に掲載された(Matsuyama & Michibayashi, 2023_Journal of Geodynamics)。

図2. 卒業研究における幌満かんらん岩体での調査の様子(2021年7月)。
この成功体験にまんまと乗せられた私は、「たくさんの試料を採取して、時間をかけて丁寧に分析すれば、すごい研究になるのではないか」と安直な発想に行き着き、修士研究を始めた。研究室配属前から野外で調査・研究を行うフィールドジオロジスト(野外地質学者)に憧れていた私は、伝統的な地質学の研究手法であるフィールドワーク(野外調査)と、近代的分析ツールのEBSDとを掛け合わせることで、「たくさんのスナップショットでマントルを鮮明に覗く」 研究を志したのである…、といえば聞こえがいいが、自分の馬力を信じて、時間コストを度外視して突き進むという力業に縋った、というのが実態であった。今振り返ってもこの選択はあまり賢い選択とは思えないが、私の性格との好相性が幸いし、期待以上の成果につながった。修士研究の内容は2編の査読付き論文として国際誌に掲載され(Matsuyama & Michibayashi, 2024_Tectoniphysics, Matsuyama & Michibayashi, 2024_Earth,Plantes and Space)、本学の学術奨励賞や日本地質学会のフィールドワーク賞まで受賞することになった。安直な発想で始まった修士研究ではあったものの、この2年間の経験により、私はフィールドワーク×EBSDという自身の研究スタイルを確立した。
そんな私が現在取り組む博士研究で設定したテーマは、「たくさんの場所からマントルを覗く」というものだ。私は博士後期課程1年の冬からフランス・モンペリエ大学への研究留学をすることになり、研究の拠点を欧州へと移した。欧州には数多くのかんらん岩体が分布し、 多種多様な“マントル地質学者”たちが研究を進めている。私はこの留学の機会を活用して、欧州各地のかんらん岩体で調査・試料採取を行い、その変形微細組織の比較に取り組もうとしている。欧州の“かんらん岩窓”からはどのようなマントルが覗けるのか、そのワクワクを原動力にして、日々の研究に取り組んでいる。

図3. スペイン北部・Cabo Ortegal岩体のかんらん岩露頭。
「地球環境科学と私」第四十八回で、竹内誠教授は「野外調査は古く,より高度化した機器分析などによる研究手法に取って代わられることも必然なのかもしれない」と述べられた。しかし私は、試料の代表性を確保できる野外調査が、高度な機器分析によって生かされる形こそが、地質学の理想形であると信じている。この研究スタイルの原点となった地球惑星科学科での学びと、岩石鉱物学研究室での日々に感謝しながら、飽くなき探究心を忘れることなく、マントル研究の最先端を突き進んでいきたい。