
★★★最新情報★★★★★★★
研究成果が、米国科学雑誌「Science(サイエンス)」で2月13日(日本時間)に公表されました。
【論文タイトル・執筆者】
Lunar
Radar Sounder Observations of Subsurface Layers under the Nearside Maria of the
Moon
小野高幸、熊本篤志、中川広務(東北大学)、山口靖、押上祥子(名古屋大学)、山路敦(京都大学)、小林敬生(韓国地質資源研究院)、
笠原禎也(金沢大学)、大家寛(福井工業大学)
「Science(サイエンス)」 13
February 2009Vol 323, Issue 5916
公式サイト http://www.sciencemag.org/content/vol323/issue5916/index.dtl
日本語サイト http://www.sciencemag.org/content/vol323/issue5916/index.dtl
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
■研究成果詳細
月の地下構造の探査を目的として「かぐや(SELENE)」衛星には月レーダサウンダー(LRS)が搭載されています。今回の論文では図1の(1)から(5)の月の海の領域を対象に、月レーダサウンダーで観測された地下構造の解析を行いました。
晴れの海(図1の(3)、直径約600km、北緯
28°東経 17°)での観測データを図2に示します。「かぐや」は月の東経約21度・高度100kmの軌道を北緯33度から20度にかけて飛行しながら、約5MHzのレーダ電波を送信し、地表や地下から反射してきたエコーを受信することによってこの解析画像(縦軸:反射面の深さ、横軸:緯度)を得ました。見かけの深さ約500mと800m付近に反射面があることがわかります。見かけの深さから実際の深さを求めるためには、電波が岩石中を進む速度を知る必要がありますが、アポロが月から採取した岩石の研究を参考にすると実際の深さは、見かけの深さの2分の1から3分の1程度になります。1972 年にアポロ17号によって月の表側のごく限られた領域で実験的なサウンダー観測が行われましたが、分解能の限界からこのような地下構造の存在は報告されていませんでした。この地下反射面は、「かぐや」が世界で初めて検出したものです。
このような地下数100m程度に存在する反射面は、図1に示した月の表側の海の何カ所かで観測されました。海の玄武岩が大規模な溶岩流として噴出して冷え固まったあと、玄武岩の上にはレゴリス(砂状の堆積物)が数10cmから数mくらいの厚さで堆積したと考えられます。さらに大規模な溶岩流がその上に流れると、図3のように溶岩層の間にレゴリス層がサンドイッチされたような構造になります。玄武岩とレゴリス層では、電波の進む速度が異なるため、このサンドイッチ構造の境界面では「かぐや」から送信した電波が高い反射率で反射されます。月表面の玄武岩層の堆積年代は、表面のクレータの研究から決定されているので、表面から連なった地下の玄武岩層についても堆積年代を決定することができます。晴れの海の南東部では、約35億5千万年前に玄武岩の溶岩流が噴出し、その後の約1億年間、レゴリス層が成長しました。このレゴリス層の上をさらに約34億4千万年前から28億4千万年前に溶岩流が覆ったと考えられます。
月の海の大平原には、細長く盛り上がったリッジと呼ばれる地形がみられます。「かぐや」で晴れの海のリッジの地下構造を調べたところ、地下の反射面は、地表のリッジの地形面と平行になっていました。海の玄武岩は粘性が低いために、冷えて固まったときには表面が水平な溶岩原をつくります。地形面と地下の反射面が平行を保って変形(褶曲)しているのは、表面の溶岩層が28億4千万年前に堆積した後にリッジが形成されたことを意味しています。従来、海のリッジは、密度の大きい溶岩層が数kmに渡って堆積することにより、その重さで地殻を押し下げたために形成されたと考えられてきました。この場合、地下層の厚さは図5Aに示すように一定にはなりません。しかし、今回の「かぐや」の観測によって、玄武岩などの地層群に数kmもの厚さはなく、また地下層の厚さは図5Bのように一定で、かつ褶曲のタイミングも従来の想定より遅いことが明らかになりました。
このことから、月のリッジは、堆積した溶岩層の重みによって形成されたものではなく,冷却によって月全体が収縮し、そのために28億年前以降、表面に皺として形成されたものとであると考えられます。今回の「かぐや」の成果は、28億年前をすぎても全球的冷却の度合いが予想外に大きかったことを示しています。
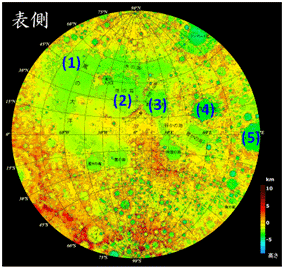
提供:JAXA/国立天文台/国土地理院
図1 「かぐや」の月レーザ高度計の観測データをもとに作成された月の表側の地形図。(1)から(5)の月の海の領域を研究対象としました。
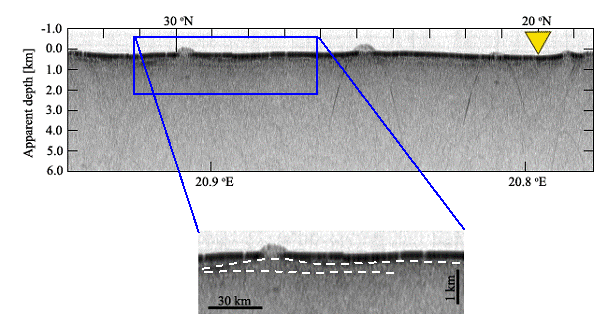
![]()
解析:名古屋大・京大・東北大
図2 月レーダサウンダーがとらえた晴れの海の地下の反射面。 表面からの強いエコーに加えて、地下の反射面からやや弱いエコーが観測されています。
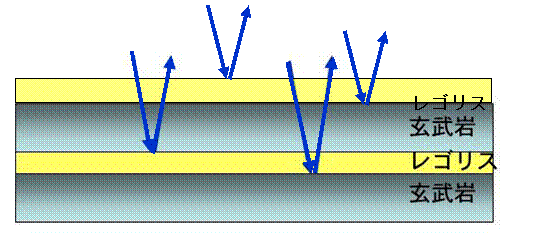
図3 地下の反射面の概念図。玄武岩におおわれたかつての月表面のレゴリス層を月レーダサウンダーが観測したものと考えられます。
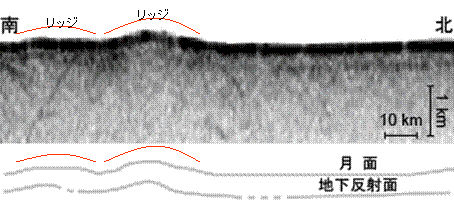
![]()
解析:名古屋大・京大・東北大
図4 「かぐや」で捉えられた晴れの海の地下構造。矢印の場所にリッジおよび地下の褶曲構造が見られます。
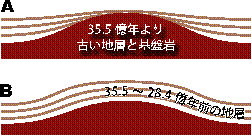
図5 堆積と褶曲の時期の違いによる、地層の厚さの水平変化を示す模式図。
(A)
背斜(上に凸になった褶曲構造)が成長しながら地層が堆積した場合。
(B)
地層が堆積し終えてから背斜が成長した場合。
「かぐや」の観測結果は地下構造が(B)のようになっていることを明らかにしました。
更新 2009.3.3