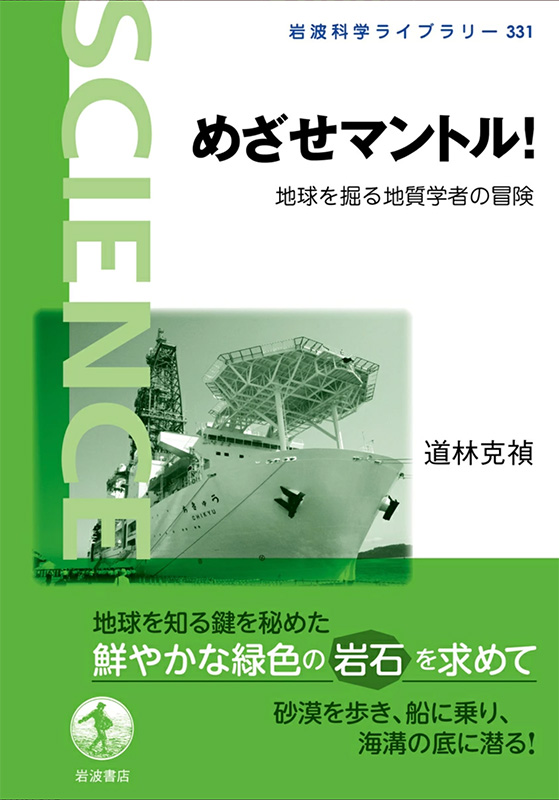
本の紹介
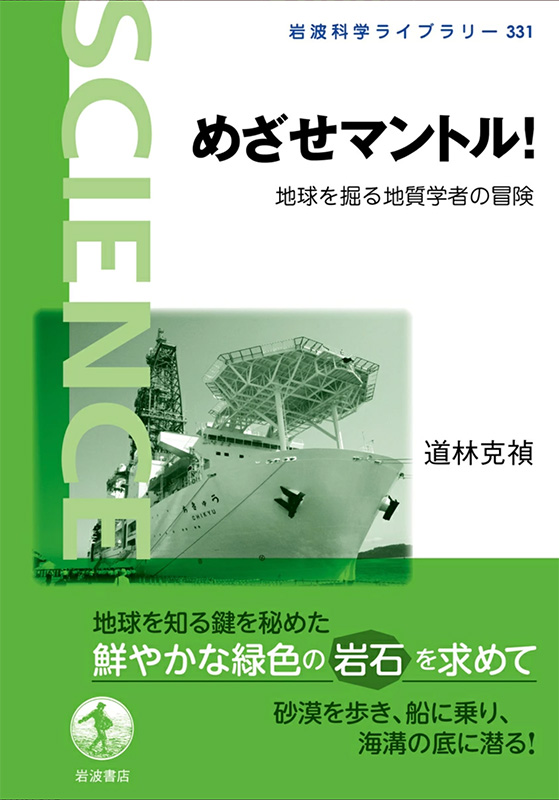
岩波書店 めざせマントル! 紹介
産経新聞 めざせマントル! 書評
日本地球惑星科学連合ニュースレター 書評
書評 道林克禎著 “めざせマントル” 岩波科学ライブラリー331 2025年 岩波書店 (2025.4.3)
(注:この書評は日本地質学会地質NEWSに掲載された鳥海光弘東大名誉教授による書評の元原稿です。長すぎたため大幅に文量が減らされて掲載されました。せっかくなので、ご本人に掲載許可を得て、ここに掲載させていただきます。)
題名から伺えるように、本書には、未踏の領域を目指す科学者の心理と途上の人間模様をあらわにしようとした内容に溢れている。しかし、それは科学者に限ったことではないのだろう。いつの時代にも、どのような方向へも、様々な先駆者が未知の領域を目指した記録が多くある。その赤裸々な経験の一コマ1コマが見事に綴られたのが本書である。その背後にある、あくなき何事かについての探究心は、著者の個性の現れであり、探究の道程で満たされない想いは、次の対象へと引き継がれ、語られていく。そして本書の終章で、ついに超深海探査へと語り終える。
著者は日本地質学会賞を受賞した代表的な地球科学者である。未踏領域への憧れと探査は研究者としての背景を基礎にしている。科学者を未踏領域と誘うのは、人の本性である好奇心のみでなく、既知の科学的知識と理論を超える発見への誘惑である。本書では、著者のこうした強烈な科学者の探究心の発露が物語として展開されていく。彼はそれを冒険と呼んでいる。確かに危険を伴う冒険でもある。
プロローグで面白いことを言っている。「なんだ、この緑の砂利は!」。後にマントル掘削と最深の海溝冒険への初学者のおどろきである。自然科学者の誰しもが経験する自然へのおどろきである。そして、第1章、“マントルと出会う、フランス研究グループのもとへ”。著者は博士号をオーストラリアのジェームス・クック大学で取得している。その後、静岡大学へ赴任した、構造地質学の新鋭の研究者であった。構造地質学は、このころ世界的には、金属物理学、物性科学、材料科学、破壊力学、レオロジーなどの広範な実験および理論そしてその応用科学を網羅して、地球や惑星内部から表層での事象へと、その対象を拡大し、国際誌上で議論の盛り上がりを見せていた。特に、プレートテクトニクスおよびマントル深部ダイナミクスの地震学的展開と物性科学的な実験とマントル岩体の調査とが大きな注目を集めていた時代である。その世界的な中心の一つがモンペリエ大学のニコラ教授のグループにあった。そこに、著者は乗り込んだのである。
本書は若い研究者や研究者を目指す若者へのメッセージを込めて書かれている。昔から言われていることであるが、第一級の世界的な研究を展開している研究グループの中に入って研鑽することは、大変大きな研究の契機であることは確かである。現在進行中の最前線の研究がどのように展開しているか。そして、その研究の動機付けと論理、観測、実験、対象の選定などがどのように日常的に展開されて行くのか。その経験はきわめて大きな知的財産となる。そして、いかに最先端研究が大変に小さいグループで行われていることに強い衝撃を受ける。また、それを可能としていることが、実は多くの世界の研究者が次々と研究グループを訪ね、そこで発表し、議論を深めていることにあると気付く。この事実を本書が次々と明らかにして行くのである。
2章のテーマは“マントルは掘れるかも”である。おりしも、2002年に国際レールゾライト会議が北海道の幌満で開かれた。世界には非常にフレッシュなカンラン岩体がある。そのうちの一つが幌満のアポイ岳にある。それはカンラン石、輝石、斜長石、などがきちんと残っていて、それらが層状に幾重にも重なっている岩体である。著者が修士学生の時にみた緑のカンラン岩の地だ。日本国内の多くのマントル起源の岩石の研究者がこの国際会議に馳せ参じた。そして著者はモンペリエ大学でのオマーンのカンラン岩研究の成果を報告する。この国際会議は大きく盛り上がり、その起源、上部マントル内部での上昇機構、マントル鉱物のレオロジーとその組織、幾重にも重なる層構造、地殻より密度の高い岩体が地殻へ持ち上げられた原因、そしてプレート運動の起源など多方面にわたる議論が行われ、その結果、地殻に現れる過程をのぞいて、現在のマントルの内部でどのような状態のマントル岩が存在しているのか。その会議で、マントルまでの掘削による探査が実行されるべきであると結論された。月の探査と岩石の採取およびその総合的研究から、大規模インパクトによるマグマオーシャンの形成とその後の惑星内部の分化による層構造の形成という新規のモデルがほぼ実証されたことにもあるように、モデル研究から実体の総合研究が飛躍的にその理解を深めることを我々は学んでいたからである。それから数年後2005年に地球深部探査船「ちきゅう」が誕生する。ムンク教授のモホール計画が国際的に前進することになる。
3章に移ると、“海溝の底でマントルをとりたい”に変わる。残念ながら、深部探査船ちきゅうはまだマントル岩の採取に成功していない。そこで、地球でもっとも深い海溝の底には今もマントルの物質が顔を出しているだろう、ならば、この目で現場を調査して、この手でその岩石を取りたい。著者はその冒険に乗り出す。しかし、問題は、海溝の底に潜水することは通常の潜水艇では不可能である。では、海洋研究開発機構の所有する「しんかい6500」ならば、というわけで、その深海潜水調査艇で、海溝へと至る巨大な海底壁の岩石を見ようではないか、ということになる。そして、伊豆小笠原海溝の海溝壁の潜水調査が実行された。著者は、本書で、その時の模様を仔細に語っている。マリアナ海溝の深海底、6469mに挑む。約3時間30分かけて沈んでいく。2mの球形の耐水球のキャビンである。その観測窓から見る海底の姿はどれほどの光景であろうか。想像を超えた未知の世界であることは確かであったろう。著者はこの未踏の地への旅路をマントルへの旅と夢見つつ、帰路にはキャビンの円窓に顔を押し付けて、海底が見えなくなるまで研究心を底へと残す。この潜航では新鮮な緑色のカンラン岩を取ることに成功した。
4章では、人類史に残るだろうマントルへの到達という一大プロジェクトの道のりがいかに困難な道であるかを思い知らされ、まさに「月より遠い道」を語ることになる。ムンク教授の提唱したモホール計画が途中で挫折し、その後、プレートテクトニクス、そしてグローバルテクトニクスの実証とその展開を深海底掘削計画によって実施するために掘削船ジョイデスレゾリューションが世界中の深海底の掘削を開始し、巨大な成果を挙げ続けた。この計画は後に国際深海底掘削計画、そして現在の国際深海底開発計画に引き継がれ、国際的な地球科学実証探査実験となった。そして、現実的に地球のマントルへと掘削する実験への大きな一歩が、日本の海洋研究開発機構で、巨大な深海底掘削開発船「ちきゅう」が建造された。
実は、ちきゅうには海底下6kmを越える掘削が可能な長大な掘削パイプを持っている。したがって、ドリルの150度を超える高温下での掘削能力と軟弱岩石と極めてハードな岩石が重なり合っている海洋地殻を掘り進めるには、長大なパイプを安定して垂直に掘削する技術が必要である。問題は両者にあり、なかなか実施に至らない。そして、さらに2011年3月11日、日本列島を襲った東北地方太平洋沖巨大地震が発生した。この歴史的な災害の中でマントル掘削計画がどのように中断し、展開したか、著者は冷静に語っている。そして、新たに、計画を練り直し、再びマントル掘削計画を始動するのに、いかに国際的なさまざまな研究者や技術者との交流とその人的ネットワークが必要であるかを、著者は繰り返し述べていく。
第5章では、それを受けて、地表に現れたマントルと海洋地殻からなるオマーン巨大岩体を掘削しようという国際計画の遂行に話が移る。題して、’マントルの痕跡を掘る’である。サブタイトルはオフィオライト掘削とちきゅう船上合宿となっている。著者はオマーン掘削計画の遂行を詳細に述べている。この章は国際的な共同研究計画を実施する際の必要な国内的準備と国際的なネットワークについて多くの参考になる事項を紹介しているので、今後の国際研究計画に参画していく上で大いに参考になるだろう。それは国際陸上科学掘削計画(I C D P)の一環でオマーン岩体を掘削しようという計画である。それはラモントドハーティ海洋研究所での国際ワークショップから始まった。そして、その大規模な掘削試料の切断、測定、そして解析に深海底掘削調査船ちきゅうの船内実験設備を全面的に使用することとなったのである。その結果、膨大なデータ群が集積し、海洋地殻からマントルに至る物質構造とその化学組成、変形組織の変化、電気伝導度変化、地震波速度変化、異方性変化、などなどが詳細に示された。こうして陸上に露出した岩体の掘削計画は大成功のうちに終わった。
そして、最終の6章、“超深海への潜航”へと至る。ある日突然、東京海洋大学の北里さんからメール連絡があり、それは、アメリカの民間研究船である、リミッティングファクターでの超深海への誘いであった。前回の海溝潜水探査は海洋研究開発機構の深海6500であった。しかし、それでは海溝底に達して目的のマントルを見ることができない。欲求不満の状態であった。それが一気にボルテージが上がった。「行きたいです。」そして物語が始まる。これぞ冒険だ。ワクワクしながらも、日程が変化するので、不安な日々が続く。そしてついに沖縄へ。潜水船の母船、プレッシャードロップ号に乗り込み、世界的な冒険家、ビクター・ベスコボさんに会う。彼が、潜水船リミッティングファクターのパイロットだ。そして、ついに小笠原海溝最深部、9789mに達する。海溝軸平坦面が見えた。「見えた、みえた、観えた。」日本人最初の最深部到達であった。残念ながら、マニピュレータが故障してしまってサンプルを取れない。無念である。しかし、目の前に広がる光景を焼き付けることはできる。さらば海溝底。
著者、道林博士はすでに日本における地球科学研究の中心にいる一人である。道林さんが本書で伝えたかったのは、研究内容の驚異的な進展がどのようになされるか、実に多くの人々の活躍と、彼らとの研究上の連携のみでなく、社会的な連携、人間的な付き合い、そして何よりも、多くの人々との、科学すること、冒険することへの、強い好奇心の共有にあるのではないだろうか。著者の楽天的でおおらかな性格が本書に随所に現れていて、科学することがこれほど人間的なものであること、楽しいものであることを、本書では実感できると思う。科学の初学者のみではなく、多くの若い人々に進める所以である。
鳥海光弘(海洋研究開発機構)